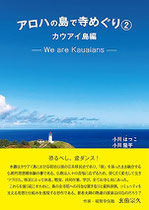


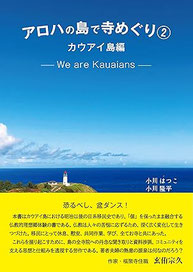
『アロハの島で寺めぐり②カウアイ島
We are Kauaians』
小川 はつこ, 小川 隆平著
2025年5月発行 A5判 226ページ 1,900円+税
・芥川賞受賞作家 玄侑宗久氏すいせん!
・小川夫婦による熱烈取材
(内容紹介)
大好評だった『アロハの島で寺めぐり マウカマカイの細道 (ハワイ島編) 』から4年。
カウアイ島編の登場です。
見どころは、なんといっても前著同様、著者夫妻による現地の熱烈取材です。
主だった12の寺をめぐり、カウアイ島と日本人移民の歴史をたどり、先人たちを掘り起こし、現在の日系人とコミュニティを描く類例なき好書です。
琵琶湖の2倍強ほどの小さな島カウアイ島は、自然に恵まれ、他民族・多文化が共存しています。
本書を読めば、カウアイ島がいかに多様性の象徴であるかを感じるはずです。
まずは、本書でカウアイ島を知ってください。
そして、カウアイ島が実現させている本当の多様性を感じてください。 さらに、本書を通じてカウアイ島を旅し、日系人のアイデンティティに触れてください。
観光旅行では知ることのできないカウアイ島を発見できる1冊です。
朝日新聞 2025年6月8日掲載
中日新聞 2025年6月23日掲載

『おしょうしな、少年の日々よ』
宍戸 ひろゆき著
2025年4月発行 46判 140ページ 1,000円+税
・おしょうしな(ありがとう)と呼べる、少年時代を振り返る、自伝的小説
(内容紹介)
敗戦からそう時間が経過していない時代、山形の小さな町が舞台の小説。
著者の少年期の体験をもとに、当時の強烈な匂いが読者を時間旅行へ誘う。
誰もが戦争で傷つき、翻弄されながらも、生きていかねばならない当時。
読後はほどよい疲労に包まれる。
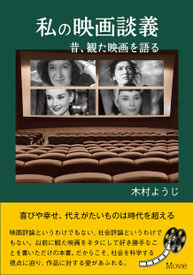
『私の映画談義 昔、観た映画を語る』
木村 ようじ著
2025年1月発行 A5判 202ページ 1,500円+税
・映画は人生を豊かにする最高のコンテンツ
・新旧の名作がずらり登場
・『ローマの休日』の裏舞台は必見
・重版出来!
(内容紹介)
映画評論というわけでもない。
社会評論というわけでもない。
著者が以前に観た映画をネタにして好き勝手なことを書いただけの本書。
だからこそ、社会を科学する視点に迫り、作品に対する愛があふれる。
名作『ローマの休日』を著者独自の視点で書き下ろした解説は本書の見物だ。
そして『女ひとり大地を行く』、『真昼の暗黒』、『眼には眼を』などあまり知られていない作品を紹介するとともに、『自転車泥棒』、『わが青春に悔いなし』、『荒野の決闘』など幅広い名作も登場する。
さらに、今だからこそ観てほしい作品として『無防備都市』、『ひろしま』、『江分利満氏の優雅な生活』、『パリは燃えているか』など社会的なテーマを含めた作品も解説する。
本書に登場する作品の数々は、喜びや幸せ、時代を超えるものばかりである。見どころだ。

